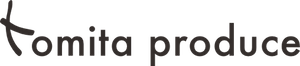SDGsは「攻めの社会貢献」?
"成長戦略としてのSDGs"って何でしょうか
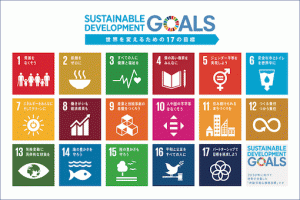
ますます多くの人が口にするようになった「SDGs」。Sustainable Development Goalsの略で、持続可能な開発目標などといわれています。2030年までに世界が達成すべき目標として国連が掲げた、貧困、安全、差別、教育機会、自然環境、経済発展と地域社会・・・などの17の「ゴール」です。
大企業も中小零細企業も、地方自治体も国家政府も地域住民も個人も・・・すべての人に関係ある考え方なので今注目されています。
しかも、ただ世のため人のための「社会貢献」ではなく、「攻めの社会貢献」などといわれ、本業を時代に合わせてより強化する側面もあるところから、経済界も自治体も政府も「成長戦略/生き残り戦術としてのSDGs」に興味をもって、何をしたら良いのかと探っているわけです。
しかし、SDGsは非常に高度な「俯瞰」の発想で考えないとよく分かりません。
国連は「17のゴールは最終的にすべて繋がっている」といいますが、普通の人には想像がつきにくい。そこでつい「うちの会社はゴール○番に取組みます」と、まさに「木を見て森を見ず…、群盲象を評す…」となりがちです。
また、中小零細企業や地方の商店街などでは「そんな余裕は無い!」と思いがちですが、これもモッタイナイ発想です。SDGsは、小さきもの、力の弱きものにも大事な役割があることを、国連が旗を振って世界に強調しているのですから、乗っからない手はありません。
SDGs企画を考えるには、まず理念を見直すこと
とはいえ、急に「SDGs担当部門」に配属された人や、これまでそんなことは考えもしなかった経営者には、やはり「難問」には違いないでしょう。
一般的には「17のゴールの中から重点的に取組む分野を決める」と指導されるのが普通です。そして、ごく単純に企業は「経済」に、行政は「まちづくり」に関して、とりあえずできることをしていくわけです。
しかし、本気で「SDGsで成長戦略を」と考えるなら、まず自社や自地域の本質価値と、「理念」や「ビジョン」から見直すことをおススメします。自社が元気に継続すると、誰がどう幸せになっているのか、無くなると誰が悲しい想いをするのか、それは長い歴史の中でどうあるべきなのか・・・といったことです。
例えば、ある町の中心の商店街が提供しているのは、各店としては野菜や魚や肉など。しかし提供価値はそれだけでしょうか? ノスタルジーや個人的な感情は抜きにして、商品さえスーパーで提供されるなら商店街には存在価値は無いでしょうか? そこをよく考えてから、企画を考えていく必要があります。
SDGsをお座敷遊び「虎虎」で理解する!?
勘違いしがちなのですが、強いものが弱い者を助けるという発想ではSDGsは理解できません。
SDGsの考え方は、例えば「じゃんけん」のようなものです。この世の中は、だれか圧倒的に強いプレイヤーがいるのではなく、それぞれが強い面と弱い面を持っているという「三すくみ」になって初めて長く続くということ。
じゃんけんだと強弱がわかりにくいので、別の例を出しましょう「虎虎」という伝統的なお座敷遊びをご存知でしょうか?
これは、舞台真ん中に衝立を置いて、片方に芸者さんもう片方に舞台に上げられた旦那が隠れて、それぞれ3つのキャラクターの何かに成って歌に合わせて衝立から出てくるという遊びです。3つのキャラとは、加藤清正(または和藤内)、虎、老母です。虎は加藤清正にやられる、老母は虎にやられる、しかし清正は老母にはかなわない・・・つまりじゃんけんと同じなんですね。これが「三すくみ」。

この遊びは誰かが勝つためにやるのではありません。
楽しく続けること、もっとやろうよ!と皆がワクワクすることが目的なんです。
現実の世の中はもっとずっと複雑ですから、三すくみどころがものすごく長い輪になっているわけですが、「生態系」と同じように誰かの存在が回り回って誰かの役に立っているわけです。
このイメージを表したものとして、SDGsの17ゴールが並ぶパネルよりもカラーホイールの方がずっと分かりやすいと思います。
そして、一対一関係ではなく3重4重の「タイアップ」企画を仕掛けていく
SDGs企画を「攻めの社会貢献」として「成長戦略」としていくには、上記の発想、社会の全体像の俯瞰、そして先の先を考えて「関係性」の輪を作っていくことが大事です。
自社の存在の「本質的な価値」が役立っている誰かを想い、その誰かの「本質的存在価値」がまた先の誰かに役立っていることを想い・・・この繰り返しです。そこにうまく、細い糸を通していくことがSDGsの企画のポイントです。
トミタプロデュースでは、「メディア化」することで顧客をファン化してビジネス展開するノウハウや具体企画をご提供していますが、「メディア化」つまり「メディアになる」ことはまさに複数他者の間をつなぐ役割になることであり、SDGsに繋がる発想で昔から仕事をしてまいりました。
ラジオの企画マンだった富田は、全国クライアントと地域のコミュニティや様々な表現者とをつなぐことは企画の根本でしたので、SDGs企画の中でも地域の問題と全国・世界の課題を繋ぐ企画が得意中の得意です。
知恵を絞って3重4重の関係者を企画に引き込んでそれぞれにメリットがある形を作って企画を成立させます。
もちろん今はラジオ局の企画の話ではありません。その発想とノウハウを駆使して、SDGs時代の企画をあなたの会社や地域のために仕立てます。
- 企業理念の見直し
- 存在の本質価値の社内ディスカス〜SDGs取組みの案だしワークショップ
- タイアップ企画の立案と進行支援
など
どうぞお気軽にご相談ください。